JMC修了生を訪ねて
花開く積極経営。南九州一円に展開
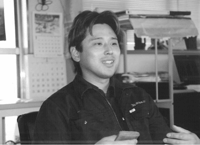 有限会社 湯前商会 専務取締役 湯前 賢二氏(JMC第65期) |
鹿児島県大隅半島のほぼ中央部に位置する大隅町。南国特有ののどかな風景が広がるこの地で湯前商会は創業した。当初は厨房設備の設計施工に軸足を置いていたが、その後、建築金物市場にも進出、手堅い歩みを続けてきた。最近では設備投資を積極的に推進してステンレス建具など建築金物の新たな分野に力を注ぐ一方、電子部品などへの進出も図っている。 その積極経営を推進しているのが今回登場いただく湯前賢二専務。生産現場を統括しながら営業活動にも積極的に取り組む湯前専務に、JMCの思い出や現状の取り組み、さらには今後の課題などについて語っていただいた。 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
後継者として受講は必須 自ら手を上げて臨む |
| 湯前専務の入社は1996(平成8)年。大分の大学を卒業後、東京の板金加工メーカーで2年間の実務を経験したあとのことだ。 「短くても5年間は他社で勉強してこいと社長に言われて東京に出たのですが、実際仕事を始めてみると自分が骨をうずめるであろう仕事場で早く頑張りたかった。早めの帰郷でしたが、入社当時はとにかくよそには負けない地域ナンバーワンの会社に育てたいという夢と意欲でいっぱいだったのをおぼえています。」(湯前専務) 1976(昭和51)年の創業以来、建築金物の製作施工を中心に堅実経営に徹してきたこともあり、湯前専務が入社した時点の社員は4名と現在の4分の1程度だった。そこで湯前専務が目指したのが湯前社長の指示を受けながらの積極経営への転換であった。湯前社長も後継の道筋がついたことでその路線を積極的に支援していくことになる。 「後継者として入社した以上は現状維持では面白くない。積極経営で仕事を増やし、南九州における湯前商会のステータスを高めたいと考えたのです。東京の板金加工メーカーで身につけたR曲げ加工技術の導入を図ったのもその意欲の表われだった。当時は周辺ではどこもできない技術でしたから、売り込みにも力が入りました。」(湯前専務) こんな闘志あふれる後継者だからこそ、当然、視野の先にはJMCがあった。自ら手を上げて受講したのは入社翌年の1997(平成9)年のことである。 「後継者としての経営感覚を身につけるのにJMC受講は必須と思っていました。ただその頃はまだ新規開拓などで忙しく1カ月近く現場を離れるのは不安があったのですが、いま踏ん切りをつけて行かないといつまでたっても実現できないと判断し、受講を決心しました。社長も背中を押してくれましたしね」(湯前専務) こうして臨んだJMCで最も印象に残っているのがインパクト研修。チーム内のメンバーそれぞれが持っている情報を互いに共有しながら一つの目的を達成するという内容だったが、そこでリーダーシップをどこでどう発揮するべきか、相手とのコミュニケーションをうまくとるにはどうしたらいいかなど、経営管理者として最も必要とする心構えを学んだからだ。 工場見学も鮮烈だった。訪問先は優れた深絞りなど高度な技術を有するプレス加工メーカーで業種的には異なったものの、モノづくりの発想そのものに感銘を受けたという。 |
現場復帰後に第2の創業へ 設備投資に営業も活発に |
| だがそれ以上に意義あるものと実感したのは受講者同士の交流。同じ立場の後継者として持つ夢や目標が刺激的だった。あまり年の離れていない同世代であったのも幸いした。 「同期のほとんどが関西や関東など競争の激しい地域でしのぎを削っている後継者で、九州の辺境から参加しているのは私ただ一人でした(笑い)。いやがうえでも触発されますよね。闘争心にさらに火がつきました」 講義のあとの雑談でもメンバーの話を聞き漏らすまいと熱心に耳を傾けていたという。短期間ながらも実に密度の濃いつきあいとなった。 当然、JMC受講を経て自社の加工現場に復帰したあとは本格的に陣頭指揮を執り、第2の創業期に突入していくこととなる。工場を拡張してシャーリングやベンダーのリプレースのほか、NCT、レーザーなどの新規導入も図るなど、生産現場は目覚ましい進化を遂げていく。営業所を鹿児島市内に設けて顧客の拡大を図る一方、都城や宮崎などにも進出、商圏も一気に拡大していった。ただ積極経営への道のりは平坦ではなかった。当初は思うように仕事を受注できたわけではなかったからだ。湯前社長も当時を振り返って次のように述懐する。 「『リスクとのバランスを考えて仕事をしているか』を常に検証する必要性をうるさくいいました。しかし若いからこそできることがあるのも事実。やる以上は中途半端なことはやるな。悔いを残さず全力で取り組めと檄を飛ばしたものです」(湯前富雄社長) |
電子部品の市場開拓に意欲 目指すは地域ナンバーワン |
| 「社長から学んだのはお客様のニーズに対して決して『できない』とは言わないこと。顧客第一の徹底でした。納期が厳しいなら徹夜をしてでも仕上げろと。信用を築いていくためには顧客の要求を確実に一つひとつクリアーしていくことが大切と厳しくいわれたことは肝に銘じています」(湯前専務) 顧客第一は営業活動にも反映されてやがて功を奏し、新規受注も徐々に拡大して積極経営が花開いていくこととなる。受注拡大とともに社員数も増え、いまや15名の社員がフル稼働の状態。顧客も南九州一円に約200社を数えるまでになった。 ただこれで満足しているわけではない。さらなる発展を目指して新規市場の開拓にも積極的だ。 「今後も建築金物を中心にしていきますが、加えて市場の大きい電子部品などの精密板金加工でのニーズ掘り起こしにも力を入れています」(湯前専務) 新規分野の開拓には湯前社長も温かい目を注ぎながら期待を寄せている。 「いまは産みの苦しみを味わっている時期なのでしょう。収益を生む仕組みをいかに早く根づかせるか、経営者として一皮むける大きな試金石といえるかも知れません」(湯前社長) 「確かに電子部品市場での競合は厳しい。要求精度もかなりハードルが高いですからね。しかし現状から抜け出しワンランク上の会社に成長させるためには避けられないチャレンジと考えています」(湯前専務) 常に前向きな姿勢を崩さない湯前専務の高いモチベーションはどこから生みだされているのだろうか。「JMCを受講したおかげでしょう。同期との出会いがなかったらここまで頑張ったかどうか」(湯前専務) これも一つのJMC効果。地域ナンバーワン企業を目指して湯前専務の全力投球の日々が続いている。 |
| ▲このページのTOPへ戻る |
|
|
| Copyright 2006 AMADA JMC |